夏になると神社の境内に「夏越の祓え」という文字が多くなるのを目にしたことはないでしょうか?
夏越の祓とは一年の半分にあたる毎年6月30日に半年分の穢れを祓う儀式です。
年末の年越しの祓とともに大祓の一つとされています。
では実際にどんなことをするのか、「夏越の祓」とは?「茅の輪くぐり」とは?どうやってやるの?などなど分からないことも多いですよね。
あわせて、「夏越の祓」にはどんなことにご利益があるのかを調べてみました!
Contents
夏越の祓とは?
夏越の祓とは、毎年6月30日に半年間の心身の穢れを清める行事です。
年末の年越の祓と合わせて「大祓」に挙げられます。
日本の神道に由来するもので主に神社で行われます。
どのように穢れを祓うの?夏越の祓
夏越の祓では「人形(ひとがた)」や「茅の輪くぐり」で無病息災を祈ります。
神社によって様々ですが、この二つのお清めの方法が多いです。
私の分身? 人形(ひとかた)とは
本日午後3時より夏越の大祓祭を斎行しました。参列の皆さまと大祓詞の奏上と切麻祓を行い、その後神前にて無病息災を祈願しました。祭典後、皆さまからお預かりした人形(ひとがた)は今津川に流しました。 pic.twitter.com/3zQXexFVox
— 岩國白蛇神社 (@shirohebijinja) June 30, 2020
人の形に切った白い紙にご自身の名前と年齢を書き、御自身の体の悪い部分(例えば、足が悪ければ人形の足の部分)と同じところを撫でて、この人形に災厄を移します。この人形が身代わりとなって、神社に奉納され、お清めが出来ます。
神社によりますが、お焚き上げをしたり、川に流したりと様々です。
夏越の祓と言えば 茅の輪くぐり
茅の輪くぐり
毎年6月30日に行われるのが一般的だけど江島神社のように一年中茅の輪が設置されている神社もあります
くぐりたい(´-`*) pic.twitter.com/bHkon8XqI2
— 天才たかぴの亜種 (@takapi1357) July 8, 2021
茅の輪くぐりは日本神話に出てくるスサノオのお話が起源とされています。
無病息災の為に腰に茅の輪をつけるというエピソードがあり、そこから現在では腰につけるのではなく「茅の輪」をくぐるということに変化したようです。
神前に建てられた大きな茅の輪を三回くぐります。詞を唱えながら、八の字にくぐることが一般的です。
②二週目もまた、正面でお辞儀をし、次は右足で茅の輪をまたぎ、右回りで正面に戻ります
③最後、三週目も同様に正面でお辞儀をし、左足で茅の輪をまたぎ、左回りで正面に戻り
④正面に戻った後、最後にもう一度お辞儀をして、左足で茅の輪をまたいでから参拝へと進みます。
くぐりながら唱える言葉ですが、いくつかあり、神社によっては掲示されているところもあります。
一部をご紹介すると、
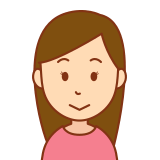
「水無月の夏越の祓する人は千歳の命のぶというなり」
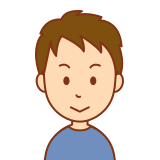
「祓い給へ 清め給へ 守り給へ 幸え給へ」
これらの詞を唱えながら茅の輪をくぐります。なかなか普段、祝詞を唱えることがないかと思いますので、覚えられるかドキドキしますね💦
茅の輪の横にくぐり方と祝詞が掲示されている場合はよく読んで、行なってみてください!
夏越の祓にいただくもの
6月30日は「夏越ごはんの日」🌾🍚 一足先に「夏越ごはん」にしました✨
夏野菜の“夏越カレー”🍛です😌💓
お米:あいちのかおり
令和3年の後半も元気に過ごせますように🎐#夏越ごはん #夏越ごはんの日 #お米 #ごはん #雑穀 #夏野菜 #夏野菜カレー #茅の輪 #夏越の祓 #richardginori #クリッパー pic.twitter.com/QSAtYEOQMi— 🌷sumin🌷 (@sumin1234sumin) June 27, 2021
夏越の祓にいただくものとして、小豆を乗せた「水無月」というお菓子があります。
また最近では「夏越ごはん」というものも登場しています。
6月30日に食べる「夏越ごはん」とは一体どんなものなのでしょうか?
夏越ごはんとは
6月30日の夏越の祓の際に雑穀の入ったご飯に茅の輪をイメージさせた丸いもの(夏野菜など様々)を乗せたご飯のことで、食の欧米化が進む日本の人にもう一度日本の食文化を見直してもらいたいと比較的最近できた行事食だそうです。
そのルーツとは?どんなものを夏越ごはんというの?
夏越の祓と同様、「夏越ごはん」もスサノオノミコトに神話に由来しています。
蘇民将来(そみんしょうらい)という人物がスサノオノミコトを”粟飯”でおもてなしをした
ということから、「ごはん」(雑穀入り)と「丸いもの」(茅の輪をイメージした)が入っていれば良いとされています。
様々な「夏越ごはん」ができそうですね。
和菓子”水無月”とは
この投稿をInstagramで見る
夏越の祓の行事食として「水無月」という和菓子を食べる風習が京都を中心に残っています。
白い三角形のういろいの上に小豆を乗せたもので、6月の時期になると京都では至るところで見かけるようになります。
小豆は邪気を払うとされており、この三角形の形も厄除けの意味があるそうです。
夏越の祓が行われる神社 5選
夏越の祓が行われる神社は多くありますが、その中でもオススメの神社を5選ご紹介致します。
①神田明神
東京都千代田区にある神田明神では毎年6月30日に数回に分けて儀式が執り行われます。
商売繁盛の神様として有名ですね。
②東京大神宮
飯田橋にある東京大神宮でも夏越の祓が毎年執り行われています。
縁結びの神社として有名な東京のお伊勢さん
毎年夕方16:00~儀式が執り行われます。
③北野天満宮
京都の北野天満宮は学問の神様である菅原道真をお祀りしている神社です。
半年の災厄や穢れを祓ってくれるほか、疫病退散を祈願したお札もお求めいただけます
④高鴨神社
奈良県御所市にある高鴨神社では旧暦の水無月(6月)にあたる7月の最終日に儀式が執り行われます。
茅の輪くぐりは終日出来、儀式は夜19:00から行われます。
こちらの人形は8月上旬に長崎県の壱岐の島に流されるということです。

⑤田無神社
埼玉県田無市にある田無神社では6月の一か月間茅の輪が設置されています。
人形は配布され、6月30日までに神社に奉納します。
6時30日15時頃より神職のみで行われる儀式により、お焚き上げして頂けます。
まとめ
いかがでしたでしょうか?季節を実感できる「夏越の祓」
日本の神道に基づくもので、一年の半分の災厄や穢れを祓えるということで
前半ついてなかったのという人や後半も頑張るぞ!という人も神社に足を運んでみてはいかがでしょうか。



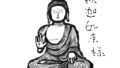
コメント